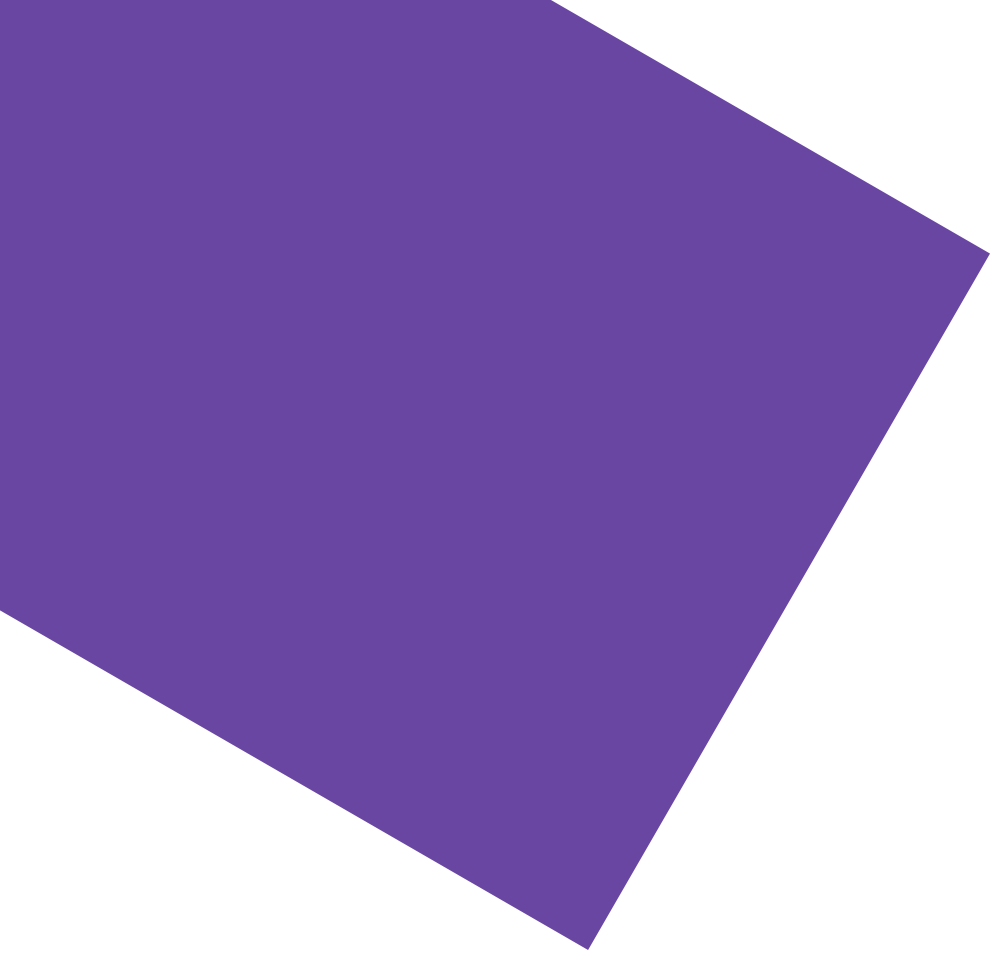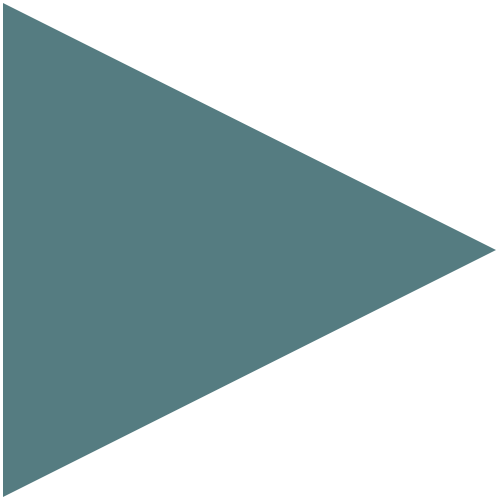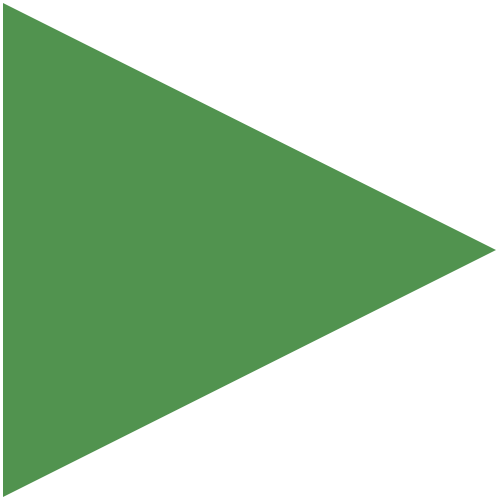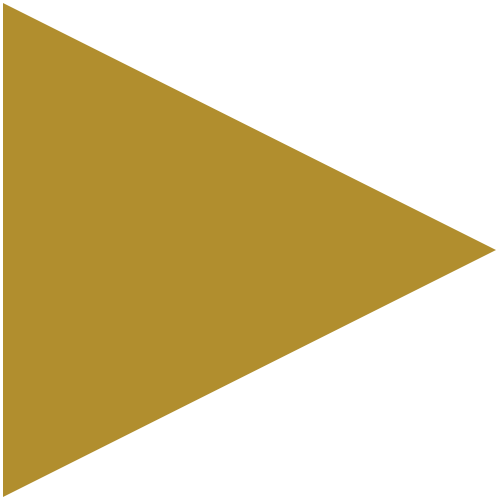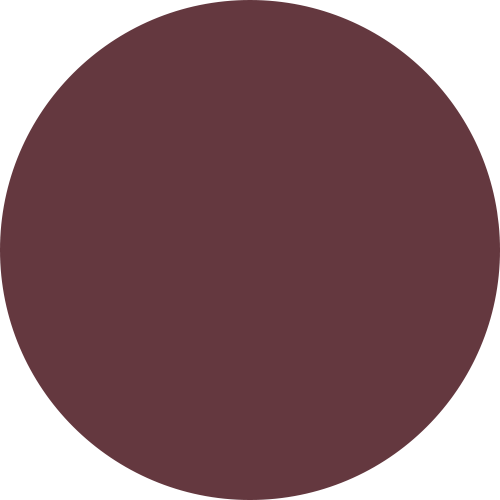NEW EP
オフィシャルインタビュー
不屈の理想も喜怒哀楽も冒険心も「音楽そのものの楽しさと眩しさ」を通して響かせることで、無限のポップ感とロックの強度を描き出す唯一無二のバンド=フレデリック。今年2月24日に開催した自身二度目のアリーナワンマン=横浜アリーナ公演「FREDERHYTHM ARENA 2020〜終わらないMUSIC〜 at YOKOHAMA ARENA」も大成功のうちに終了、さらなる快進撃への期待感が熱く沸き返る――という状況は、折からの新型コロナウイルスの感染拡大による外出自粛要請によって一変。ライブやフェスなど音楽に限らずあらゆる大規模イベントが中止・延期を余儀なくされ、誰もが「その先」のビジョンを今なお手探りで模索している。
しかし――フレデリックはその歩みを止めなかった。メンバーがスタジオに集まることすら叶わなかった春先から、三原健司・三原康司・赤頭隆児・高橋武の4人は個別の環境でリモート制作に突入、ついには4曲の新曲を収録した新作EP『ASOVIVA』を完成させるに至った。7月18日に配信されたアコースティックオンラインライブ「FREDERHYTHM ONLINE『FABO!!〜Frederic Acoustic Band Online〜』」からのテイクも含め、この混沌とした時代の中でも、いやこの時代だからこそ、そのクリエイティビティと情熱の限りを尽くして「遊び場」を開拓し続けるフレデリックの姿は、それ自体が希望そのものとして映る。4人にじっくりと話を訊いた。
(インタビュー:高橋智樹)
―― まずは、2020年の足取りを振り返っていきたいんですけども。フレデリックにとってもエポックメイキングな出来事だった2月24日の横浜アリーナワンマンから半年、あのライブに関して今改めて思うことは?
三原健司(Vocal & Guitar): 横浜は武ちゃんの地元っていうのもあって、自分たちにとっても思い入れの深い場所でもあったし。でもその中で、メモリアルなものにし過ぎるのもよくないと思っていて。自分たちのバンドの中での軌跡を見せつつも、「まだこの先に道が続いていくんですよ」っていうテーマ性を見せたいなって思った時に――自分たちは音楽が好きで、音を鳴らしている瞬間っていうところに意味を感じてバンドをやってきた4人なんで。そこをもっとフォーカスする、音楽の中でちゃんと伝えていくものを見せたいなっていうのがあっての「終わらないMUSIC」っていうタイトルだったんで。そこからずっと半年間ずっとライブができないっていう、まさかの予期せぬ事態にはなってるんですけど……2月24日に「自分たちの音楽はこうであって、この音楽を通して自分たちは30歳、31歳、これからの人生を歩いていきますよ」っていうものを提示できたワンマンだったなって、自分では感じてますね。今のこの状況の中で、より意味を成したワンマンになったなっていうのは、日々過ごしていて感じます。
三原康司(Bass & Chorus): 今となっては恋しい部分もあって。あれだけのお客さんを入れて、横浜アリーナっていう場所で音を響かせることって――そこに向けて1年かけて歩んできたバンドだし、健司の言う通り、チームとして音楽のいろんな歩みがあった中で、「そこにまた戻っていきたい」とか、いろんな恋しい部分を感じて。もっともっと、どんどんそれを大きく広げていくことに対して、次に向けて頑張っていこう、とも考えていたところやったんで。そう思うことって、ひとつの向上心でもあるのかなって思いながら過ごしてましたね。
赤頭隆児(Guitar): バンドを始めてから毎週ライブがあったりする感じで、夏は週末はずっとフェス、っていう生活サイクルみたいなものがあって。それが当たり前みたいになっとったけど、なんかもう、なくなってみたら――「あれって良かったなあ」ってめっちゃ思って。最後に普通にできたライブが横アリだったんで、余計に「もう一回やりたいなあ」って思います。
高橋武(Drums): 実際に映像を観たりして振り返る機会が多かった中で――普段、自分たちで作った音楽を、しばらく時間が経ってから聴き返して「違う聴こえ方がする」っていう経験って、どのアーティストでも誰でもあると思うんですけど。僕はその感覚を、横浜アリーナの1ヶ月後ぐらいに映像を観た時点でものすごく感じていて。状況が変わったっていうことももちろんあるんですけど、自分たちの音楽の聴こえ方が変わってきたのはすごく新鮮だなと思っていて。そういう自分の中の変化が『ASOVIVA』だったり、これからさらに活動していく上での糧になっている感じがすごくしたんですね。でもそれって、僕たちだけの話でもないと思っていて。SNSでも「フレデリックの横アリが実際に行った最後のライブ」って書いてる方も結構いたりして。狙った形とは違うと思うんですけど、僕たちと、ライブに来てくれた人と、来れなかったけど映像作品を観てくれた人と、気持ちを共有できてるなっていう感覚があって。普段の「ライブで気持ちを共有する」っていうのとは別軸の共有の仕方があったなと思うんですよね。そういう心境の変化って、音にもつながってくると思うんで。
―― あの横アリの後、新型コロナウイルス感染拡大防止のための外出自粛で生活は一変しました。ステージに立つことを日常としていたバンドやアーティストにとっては本当に、生活どころか価値観そのものが変わるくらいの激変を迫られる状況だと思うんですけども、そういう環境下で不安や虚脱感を覚えることはありましたか?
康司: ただ、そうなった時に――いろんなことを悩んだりすることもあると思うんですけど、やっぱり「できることって絶対あるな」と思って。それですぐさま制作に手をつけられたのが『ASOVIVA』だったんで。そうなった瞬間に、「じゃあ、自分たちの自宅に機材を揃えて、今までのレコーディング形式を変えて、何かを作り出そう、始めよう」って思えたんで。やるべきことは決まってたんで。僕らが日常の中で、ライブハウスだったりフェスだったりで音楽を鳴らすように、また音楽を作って、そこに前向きに希望を持って、「次に何を出そうか」っていうことにまっすぐ向き合えてる自粛期間だったと思います。
―― ちなみにみなさん、外出自粛期間はどういうふうに過ごしてました?
康司: 僕は、ずっと走ってました(笑)。3ヶ月間ずっと走っていて、1ヶ月100kmペースで。昔、陸上部の経験もあったんで。やっぱりバンドって体力勝負な部分もあるし、すぐに自分たちが動き出せるように、何かやっとかなきゃなって。自分を掻き立てる部分もあって――っていうか、ただテンション上がるから走ってた部分もあるんですけど(笑)。
健司: 康司と同じように運動もしつつ、今まで忙しくてやれなかったことに手を出そうと思って――パソコンを買い替えたりとか、録音機材を買ったりとか。それこそボーカルブースを買って、家で練習したりとか。あと、動画の編集みたいなところも勉強してみたりもしましたね。みんなが外に出れない中で、自分たちができることって、音楽を作るだけじゃなくて、動画での発信も大事だなと思っていたので。
赤頭: バンドのインタビューで言うほどのことでもないんですけど(笑)、映画をいっぱい観てましたね。1日に2本とか3本とか観てたんで。俺、感動したいんですよね、映画で。だから、あんまり今までコメディとか観てなかったんですけど、コメディも観てみて――「コメディって、そんなに笑いを取ろうとした映画ばっかりじゃないな」と思って。感動を狙ったり、バトルがあったりするわけじゃないけど、なんかグッとくる終わり方をするものが多いなって。『ラストベガス』が良かったですね。あと、コメディじゃないけど『マイ・インターン』も良かった。どっちも同じ人(ロバート・デ・ニーロ)が出てるんですけど。
高橋: 外出自粛期間になって最初に考えたのは、リモートで制作が始まるとしたら、たぶん一番悩むのって「ドラムのレコーディングをどうするか」だなって。生音かそうじゃないかで、一番変化が大きい楽器なので。だからもう、ひたすら電子ドラムのことを調べてましたね。来るべき時にちゃんと準備ができてるようにしたかったんで。「じゃあ制作しよう」ってなる前に買ってました(笑)。
―― 実際、今回の『ASOVIVA』の新曲はリモート制作でレコーディングされたそうですね。リモート環境で制作が始まったのはいつ頃のことでした?
健司: 4月ぐらいかな? 春にはもう「スタジオに入れたらいいけど、もしかしたらリモート制作になるかもね」っていうことも頭に入れて準備してましたね。
赤頭: 絶対家で録るかまだわからへんけど、最初に機材買ったんやもん(笑)。デモ用に一応、家にも持ってたのは持ってたんですけど、「そのままCDとか配信の音源になるんやったらちゃんとしたの買おう」と思って、新しく揃えました。
康司: メンバー同士、バンドでのやり方を常に話し合ってきたので。ライブで演奏する時、お互いに見なくても「ここはこう合わせるんだろうな」みたいな――言わなくてもわかってくれる感じが、リモートのやり取りの中でもあったので。だからこそ意欲的に「新しいものに挑戦しよう」って踏み込めたところはありますね。
高橋: でも、バンドが始まってすぐとか、俺が加入してすぐとかだったら、こんなに上手くは行ってないと思うし。お互いが考えてることをわかった上で、今までの経験があったからできたことだと思いますね。
■『ASOVIVA』全曲解説インタビュー
―― 今回の作品を「ASOVIVA(遊び場)」と名付けたのは?
健司: 僕はフレデリックっていうバンドの魅力というか「好きだな」と思うところって、ひとつの言葉でいろんな可能性を作れることやなと思って。それこそ「フレデリズム」とか「TOGENKYO」とか――「TOGENKYO」っていう言葉だけでひとつの世界観を作れるし、そこから発信するものがどういうものでも、自分たちの面白い世界の中に留めることができる。可能性が広がる言葉が多いなと思って。そういうところを考えた時に……自分たちも30代、バンドで言えばこの9月でメジャーデビュー6周年っていうところで、新人と言える立ち位置ではないけど、まだまだワクワクさせるバンドでいたいなって思うし。自分はその「広い言葉」っていうところに魅力を感じているからこそ、今のフレデリックがどういうものを提示したら面白くなるんだろう?って考えた時に、「遊び」っていう言葉が出てきましたね。これはフレデリックの楽曲の中にもある言葉だと思ってるんで。その中で、もっと広い言葉っていうところで「遊び場」っていう。来年2月には日本武道館ワンマンも決まっているし、武道館っていうところを「遊び場」にしたら面白いんじゃないかなって。
01.Wake Me Up
―― 特に“Wake Me Up”“されどBGM”は、「フレデリックのダンスミュージック再解釈&再定義」的な意味合いを強く持っている楽曲で。生ドラムの鳴り感とかに象徴される「バンドサウンドっぽさ」ではないところで、フレデリックというバンドのアイデンティティが“Wake Me Up”には結実している気がするんですが。
康司: 今回「遊び」っていうテーマがある中で、自分たちがいわゆる「日本人が惹かれる音楽性」とか「ロックバンドのあるべき姿」とかそういうものじゃなくて、サウンド感としても新しいものを、っていうことに対して自分はすごく考えましたね。「バンドであること=4人だけで鳴らす音」っていうイメージじゃなくて、ずっと僕らは音をかぶせたりとか、いろんな音の中で情景とかを表現してきたバンドなので。だからこそ、その中での可能性を自分たちで見出していくことこそ、俺はミュージシャンらしいなとすごく思ったので。同じことをするより、今までを糧にして、サウンドにしろメッセージにしろ、これから新しく見出していくことが大事だなって。この曲の歌詞を書く時も、「生まれ変わる」っていうワードを想像しながら書いていたし。そういう意味でも新しいサウンド感だったり、こういう再構築されたダンスミュージックになっていったんだなって思います。レトロフューチャーというか、昔ながらの歌謡曲チックなところから、またちょっと洗練されて、結構洋楽チックなサウンド感になっていて。キックの大きい感じとか、ミックスの方向性とかも、洋楽のダンスミュージックに近い軸があると思いますね。
―― 途中で拍が変わったり、かなりアクロバティックなリズムですけど、楽しんで叩いてる感ありますね。
高橋: おっ、それが伝わってるなら嬉しいですね。制作の順番で言ったら、この曲の前に“されどBGM”を録ってるんですけど。その時に実感したのは――音色だけじゃなくて、ドラムを叩くタイミングで「その人らしいノリ」ってめっちゃ出るなって。なので、“Wake Me Up”ではリズムの捉え方を変えてみようと思って。レコーディングの時って普通はクリックを1拍ずつ、1小節に4回聴くんですけど、俺はほとんど小節のアタマしか聴いてないんですよ。で、ここの拍は突っ込む、ここの拍は大きく取る、って作っていて。普通に聴いたらめっちゃ気持ちいいと思うんですけど、クリック鳴らしながら聴くとやばいですよ(笑)。
02.されどBGM
―― この曲がリモート制作の最初の曲ということですけども。サビの印象的なフレーズをシンセのフレーズに任せるっていう、どちらかといえばEDMとかハウスとかのマナーを感じさせる曲でもありますね。
康司: アクセントとなるものがずっと曲中で鳴り続けてる心地好さって、洋楽の中でも結構あって。日本で言えば「サビメロが戻ってくる」みたいな感じなんですけど。やっぱりループミュージックっていう言葉を何度も何度も使ってきてるバンドではあるんですけど、そういう基軸みたいなものに沿って、アイコンっぽくなるフレーズがあった方がいいなと思っていて。そこから生まれたものですね。
―― 《たかがBGM されどBGM》っていうフレーズには、拳を掲げない闘争宣言というか、ものすごくポップな形で「でも何かに抗う意志は持ってるよ」っていうことを表明するような熱量がありますよね。
康司: 僕ら自身は「されど」で音楽を考えるわけですけど。この自粛期間の中で、僕らだけじゃなくていろんなミュージシャンだったり、音楽を愛してくれてる人たちが、音楽っていう存在に対して向き合う中で――「本当にこれって必要なものなのか?」って。それは音楽だけじゃなくて、いろんなことに対して考えたと思うんですよ。でもやっぱり、僕らは音楽を生業にしている以上、音楽に対する奇跡というか、たくさんのお客さんが一緒に音楽を楽しんでいるっていう光景を見てきた中で、自分はそれを不必要やとはどうしても思えなくて。そこから生まれてきて、バンドがずっと続いてきているので。たとえ不必要なものやと思われたとしても、それを必要と思う気持ちだったりとか、それに対して希望を見出せる想像力って、人間にとって一番必要なものなんじゃないかなってすごく思うんです。音楽を聴いて、何かしら力が湧いてくるとか、未知の感情になることって、すごく不思議で、かつ希望に満ちたことであって。そういったメッセージをミュージシャンとして、音楽を通してやっていくことが大事なんじゃないかなと思って。祈りに近い、みたいなところはありますけど……そういった楽曲を、俺らがやっぱり出すべきなんじゃないかなって思ったんですよね。
赤頭: 今までも音楽がテーマの曲っていっぱいあって、「康司くんが音楽に対してどう思っとるか」みたいなものって、メンバーだけじゃなくてお客さんにも伝わっとると思うんで。でもそういう、音楽を歌った曲の中で、今までで一番「これを聴いて」っていう気持ちが強い印象を、僕はデモの段階で受けて。これが一番届けばいいなって思います。
03.正偽
―― 一転して“正偽”では、ファンキーなビートの中で康司さんのシニカルサイドが炸裂していて。キレキレのサビで《黙れ フィーリング 印 埋葬》ですからね。
康司: (笑)。サウンド感にフレデリックの多幸感が出てる中で、感じること、疑問視していることに対してメッセージを詰め込んでいくことって、今までもやってきてるんですけど……この曲が一番出てる気がします(笑)。いろいろ生活が変わってきた中で、お互いの正義とか、互いに自分が信じるものがあって。それって誰が正解とかじゃなくて、討論し合っていく中でみんなで盛り上がっていってる状況で。今って話題性とか「面白ければオッケー」みたいなことって結構あると思っていて。それって楽しめる一歩でもあるけど、悪用にも繋がるし、そのためにやる人たちもいるし。それって俺、本当に好きじゃないなってずっと思ってて。そういう人たちって、何かを信じようっていう時に聖書を開くわけじゃなくて、検索するんですよ。そこで自分が正しいと思うものを見つけるっていう。それって結局、「誰かが集めた統計」の一番正しいものなんですよね。そうじゃなくて、ミュージシャンとか人と接する仕事をしてる人たちって、自分たちで体感したものを信じて生きてると思っていて。目の前で起こったことを体感して、それを信じて生きている自分自身こそが、俺にとっての真実だってずっと思っていて。簡単に出てくる正義感を疑うことって、めっちゃ大事だなって。窮地に立った時とか、大変な時とかに、そういう部分がすごく表に出てきたりして。「これは音楽にすべきじゃないかな」って――結局これも、俺のエゴでしかないし、俺の正義でしかないし、誰かにとっては間違いだとは思うんですけど、こういう形で音楽を届けることが、自分のやれることやなって。
健司: 歌詞の中では皮肉っぽいマシン感が出てる部分もあると思うんですけど、それを自分の声で落とし込むと、もうちょっと聴きやすくなるなと思って。自分の声って良い意味で「どういう言葉でも軽く聴こえる」、聴きやすいところに落ち着くところが良いと思っていて。フレデリックの歌詞って、結構シニカルな表現って多いと思うんですけど、自分の声が中和して面白い方向に連れて行ってるなと思いますね。
高橋: この曲では「ビートを2ステップっぽくしたらいいんじゃないか」っていう話になって、1時間半くらいこの曲のデモを流しっ放しにしながらずーっと電子ドラムを叩いて、そこから切り取ってビートを組んだんです。自分でブレイクビーツを作ろうって。
赤頭: でも、「2ステップの参考に」ってみんなが聴かせてくれた曲が、ことごとくギターが入ってない曲で。そうなった時に、もう遊ぶしかなくて(笑)。「何やっても正解なんちゃうかな」って。Aメロは機械的な感じでわざとコンプ強くかけて、サビのカッティングはちょっとだけルーズに――人間っぽい「強弱が出てしまっとる感じ」にしました。
04.SENTIMENTAL SUMMER
―― “SENTIMENTAL SUMMER”は、1曲の中にふたつの異なる景色があって。エレクトロっぽいパートと、サビのバンドサウンドのパートが寄せては返すような展開の楽曲になってますよね。
康司: “SENTIMENTAL SUMMER”は、夏フェスのことだったり、それに近い部分で言えば甲子園だったりとか……全然違うと思うんですけど、ありがたいことに僕らはフェス常連バンドとして、今までいろんなフェスに出演させていただいて、直接何万人っていう人との出会いがあったりして。その中で音を鳴らしたり、自分たちのメッセージを届ける場があって。それが変わってきた中で――たとえば甲子園でも、高校生が一生懸命そこを目指していくわけで。フェスを目指すことも「大きいステージに向けて」っていうのも、自分たちの中でひとつ青春のストーリーとしてあって。それがこういう状況でなくなってしまった時に、「その夏に対して歌いたい曲」を俺はここで作っておくべきじゃないかなって思ったんですよね。
健司: “砂利道”とか“トライアングルサマー”とか、フレデリックで康司が表現する「夏」って、俺の中では風景が見える曲が多いなと思って。“SENTIMENTAL SUMMER”はじりじりするような温度をすごく感じる曲だなと思ったので。Aメロのひんやりしたスッとした歌い方とか、サビのエモーショナルな感じとか、そういう温度感は意識しましたね。こういうAメロの歌い方って、フレデリックの楽曲の中で使ってなかった要素なんですよね。ちょっとミックスボイス寄りみたいな。この自粛期間中に習得したようなところもあって。こっちで歌った方が、歌詞の聴き取りやすさとか、1オクターブ下で歌ってる自分の低音とかを際立たせることができるので。
高橋: 前半のハーフテンポのところは差別化したかったんで、TR-808を使ってますね。808を生ドラムに重ねることはあったんですけど、808単体で使うことは今までなかったんで、それも新しい試みだったなって。
05.リリリピート(FAB!!) /
06.ふしだらフラミンゴ(FAB!!)
※Live at FABO!! 2020
―― この“リリリピート”と“ふしだらフラミンゴ”の2曲は、7月18日に配信されたアコースティックオンラインライブ「FREDERHYTHM ONLINE『FABO!!〜Frederic Acoustic Band Online〜』」からのライブテイクです。実際に「FABO!!」をやってみた感触はどうでしたか?
健司: 「新しい可能性を発見できたな」っていうのは思いました。ライブハウスとか野外フェスとかでやった時の感動って、オンラインライブでは絶対に味わえないと思うし、代わりには絶対にならないと思うんですよ。ただ、逆に考えると、オンラインライブでしか得られないものって絶対にあると思っていて。スピーカーとかイヤホンで聴いたり、アーカイブがあれば朝聴くこともできるし、「自分で楽しみ方を選べる」っていうのがオンラインライブの良さのひとつだと思うんで。そうやって聴いた時に、「こういうアレンジしてたんだ」とか「本当はこういうメロディを歌ってたんだ」っていうことを感じてもらいやすいのがアコースティックライブなのかな、っていうことでやってみたんですけど。「フレデリックってこういうこともできるんだ」って自分でも感じましたし、こういうアコースティック編成でもっとやりたいなって感じてますね。フレデリックがオンラインライブをもっと開拓していくアーティストになれるんだろうなって。
康司: 健司が歌う声がすごく響く場がアコースティックで。言わばオンラインって、コロナの状況になる前からあったものではあるんですけど、その中で「ミュージシャンだからこそできる提案」っていっぱいあるなと思って。オンラインはオンラインで、新しい楽しみ方だなって思うし。お客さんがいない状態で、「こういうふうに観てくれてるのかなあ」「パソコンかiPhoneで観てるのかなあ」って想像しながらやるんで(笑)。そういうことを想像しながらやるのも、距離を近づけようっていう気持ちの寄せ方ひとつなんかなあと思ったりするんで。
赤頭: 思ったよりライブやったなあって。「ライブっぽくないんかなあ」って思ってたんですけど、終わった時の感じが、ライブ終わった時とめっちゃ似とって。もちろん、画面の向こう側を想像もしたんですけど――あの日は4人向き合ってやってたんで、「4人でやっとる感じ」もあって。何より、楽しんでできたのが一番よかったなあって。それが伝わればいいなというか。
高橋: もう楽しかった!って――語彙力なくなるくらい「楽しかった」が先に出ちゃうのが正直な気持ちで(笑)。アコースティックって、それぞれの音がより繊細に見えるじゃないですか。フレデリックって、メンバー同士の音での会話がすごく多いんで。それは制作においてもそうだし、ライブでもそうなんで。その音の会話っていうのが、あの日のオンラインライブでもものすごくメンバー間であったし、それが観てる人にも伝わりやすかったんだろうなって思いますね。
―― 9月27日にはオンラインライブ「FREDERHYTHM ONLINE「ASOVISION〜FRDC × INT〜」、10月からはライブハウスツアー「FREDERHYTHM TOUR 2020〜たかがMUSIC されどMUSIC〜」もスタート、来年2月23日には日本武道館ワンマンライブも予定されています。
健司: 「2020年ってこういう年だったよね」っていう印象って、たぶんみんな同じじゃないですか。だからこそ、この大変な年にフレデリックは何をしていたのか?ってすごく大事だし、その中で何を大切にしてきたかっていうことが、ライブでより鮮明にわかってくることだと思っていて。でも、フレデリックにとって一番大切にしてきたことって、今までと変わることなく「音楽で遊ぶこと」だし、それはこれからも大切にしていくことだと思っているので。それを受け取る人にメッセージを伝えるとしたら――「楽しみに待っててくれ」っていう、シンプルな言葉に尽きますね。