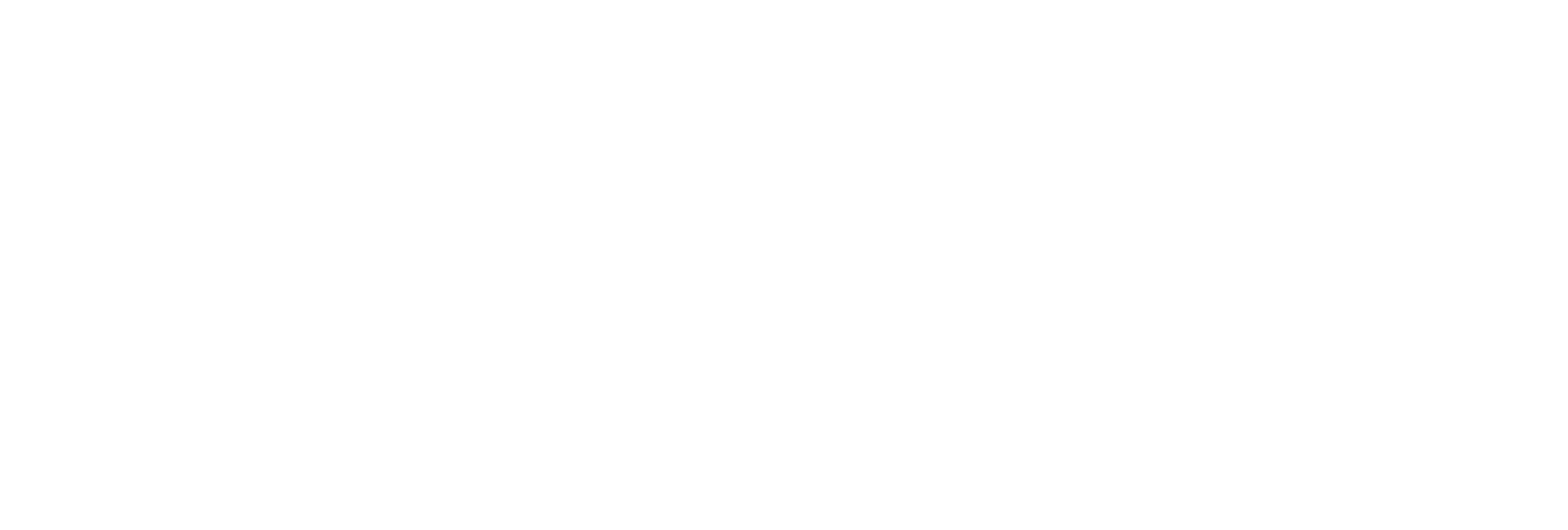
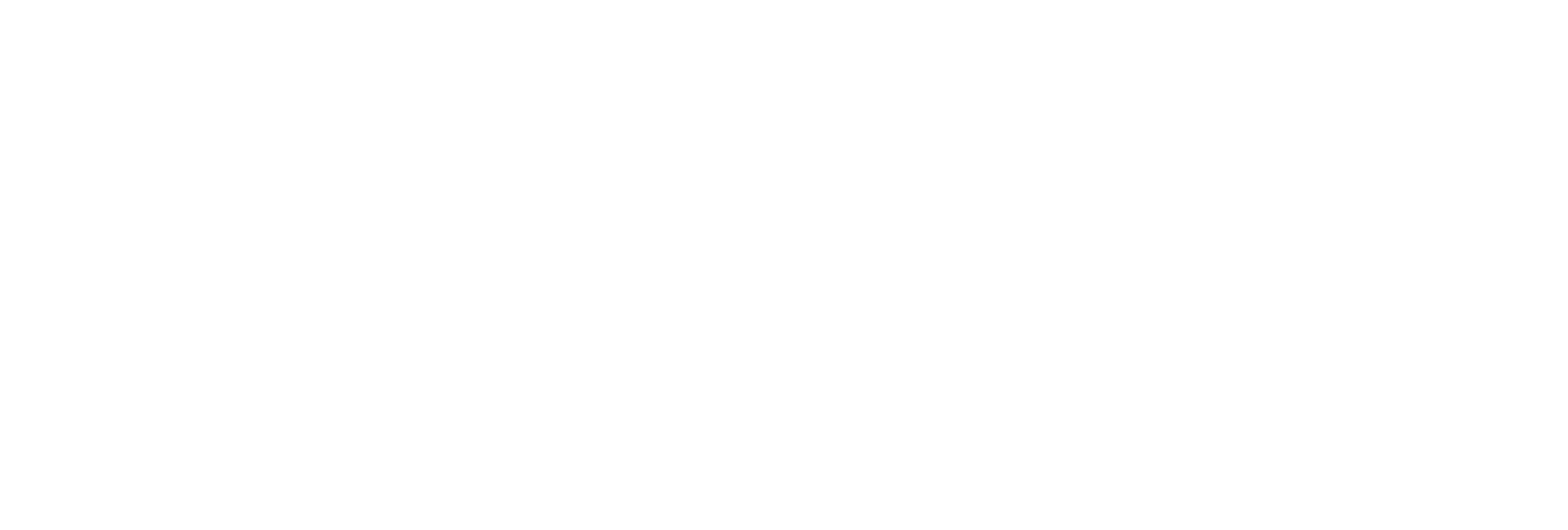
INTERVIEW
――2023年2月にリリースされた『優游涵泳回遊録』以来、約1年9カ月ぶりのミニアルバムになります。収録された8曲は八曲八様と言っていい、とてもバラエティ豊かな楽曲達であると同時に、それぞれに趣向を凝らしたアイディアが盛り込まれた非常に充実した、かつ現在のフレデリックのアティテュードやメッセージが強く現れた作品だと感じました。まずは4人それぞれ、今回の『CITRUS CURIO CITY』という作品に対してどんな手応えを感じているのか、というところから行きましょうか。
赤頭隆児「手応えか……やりたいこと、できることが日々変わっていってるというか、増えていってることがいいことやなって自分では思ってて。たとえば全然ジャンルが異なるものでも、バンドの中で『次はこれを試してみようか』とか『ちょっとこういうことをやってみたいんやけど、どうかな?』みたいな会話を楽しみながらできる。それは昔からそうなんですけど、今も本当にそうやって音楽に取り組み続けることができてるんですよね。毎回フレデリックとして作品を作る度に、康司くんがやりたいことをどう実現できるか――自分があんまり聴いてこなかったタイプの音楽でも康司くんに教えてもらって聴いて、じゃあこういうのはどうかな?って考えて試してみて、そういうことの繰り返しで自分の音楽の幅が広がっていって、日々できることが増えてきた音楽人生なんですけど、今回もそれが凄くたくさんあったなと思います。ミュージシャンとして楽しく、充実感を持ちながら作れたアルバムやと思いますね」
三原健司「僕は今回、めちゃくちゃいい意味で『抜群の安定感を誇る曲がない』、だからこそ今後、面白い景色を見せてくれるアルバムになったんじゃないかなと思ってて」
――その「抜群の安定感を誇る曲がない」というのは、どんな意味で?
健司「自分の中でその基準はライヴなんですけど、たとえば前回の『優游涵泳回遊録』でいったら“スパークルダンサー”は完成した時点でめちゃくちゃライヴが見えた――自分がライヴでどうこの曲を押し上げていくのかやったり、ライヴでこういう景色になるんだろうなっていうのが見える曲やったんですよね。で、今までの僕らのアルバムって、そういう抜群の安定感を誇る曲が作品のひとつの軸になっていたところがあると思ってるんですけど、この『CITRUS CURIO CITY』に関しては、どの曲も『この楽曲ってライヴでどういう景色になんねやろ?』と思う、いい意味で予想がつかない部分が多くて。それはつまり、どの曲も自分達の新しい境地に行ってる感じが見えるってことだと思うんです。もちろんフレデリックらしい要素はどの曲にもあるし、全部が新しいことをやってるというわけではないけど、でも、この曲達をもってライヴをやった時にこれまでとはまた違った場所に辿り着けるんじゃないか、みたいな期待が凄くあって。自分達が今まで大事にしてきたものをもう一度見つめ直すことができるやろうし、同時に、まったく新しい自分達を見つけることもできるんやろうなっていう期待値がもの凄く大きい。そういうアルバムやと思います」
――作っている段階から、そういうことを感じてたんですか。
健司「感じてました。最初から『これはライヴの流れを変えてくれそうな曲やな』っていうのはずっと思いながら作ってた曲達なんで。それが8曲集まったなっていう感じですね」
――では、武くんはどうですか。
高橋武「隆児くんと健司くんが話してくれたことは自分も感じてるんですけど……でも僕は何より、ホッとしたという気持ちもめちゃくちゃ強いです」
――ほう。それはどうしてなんでしょう?
高橋「たぶん自分の考え方がちょっと変わってきた部分もあって。結論としては隆児くんが言うように、自分達がやりたいこと、日々新しく吸収していることをどんどん表現していくことが最善の形だという考えはあった上で、自分達も35歳になっていろいろと経験を積んだというのもあって。……やっぱりミュージシャンって、みんな当たり前に努力をしてるじゃないですか。本人がそれを努力と思ってるかどうかは別として、音楽をよりよくするために日々それぞれに精進してると思うんです。でも、どれだけ努力したからといって、必ずしもそれがいい作品に繋がるとは限らないし、あるいは去年カッコよかったから今年もカッコいいとは限らないという、残酷な側面もあるなと思ってて」
――はい、そうですね。
高橋「自分はライヴを観るのも好きだからいろんなライヴを観にいってるんですけど、演奏は拙いけどめちゃくちゃ感動するライヴもあれば、逆もあるし。そう考えると、僕はバンドをよくするためにと思って日々練習もしてるしインプットも増やしてるけど、それがバンドにプラスに働くのかマイナスに働くのかは、正直、出来上がってみるまでわからないところはあるよなっていう視点も最近はあって。もちろん、それでも結局、自分がいいと思うことを信じてやり続けるしかないんですけど。そういう中で、康司くんが書いてきてくれた曲に対してフレデリックとして今の最善の形をちゃんと作れるのかっていうのは、期待と同時に不安……いや、不安とはちょっと違うんだけど、なんて言うんだろう、難しいな」
――少しドキドキしてしまうような、期待はあれども絶対に大丈夫だと楽観的にはなれないような気持ちがあった?
高橋「うん、そうですね。緊張感があったということかな。要は油断してなかったということでもあるんですけど。だから『CITRUS CURIO CITY』が完成して、ちゃんと康司くんの気持ちとか、バンドの伝えたいことを今回もちゃんと表現することができた、自分としてそこに応えることができたなって安心できた部分はありましたね」
――言い換えれば、武くん自身がおっしゃっていた通り必ずしも努力が実るとは限らないし、自分がプレイヤーとして成長していくこととバンドが輝くことは必ずしもイコールではないけれど、でもこの期間に自分が積んできた進化とインプットがちゃんとフレデリックを輝かせる形に着地できたという安心感がある。
高橋「そうですね、それは終わってみて再確認できました」
――それでは、康司くん。『優游涵泳回遊録』をリリースしてから少しインターバルが空きましたけど、そもそも、次にどういう作品を作りたいと思ってこの作品に取り掛かり、そして実際にどんな作品ができたなと感じているのか、教えていただけますか。
三原康司「結果的には、この『CITRUS CURIO CITY』はフレデリックが今、心から好きだと思えるものが詰まった作品になったなと思っているんですけど。………前作の『優游涵泳回遊録』は、自分としてももの凄く好きな作品を作ることができたんですよ。完成度にしても達成感にしても凄く大きなものがあったし、フレデリックがこれから目指していく志みたいなものが凄く詰まった1作でもあったと思ってて。だからこそ、『優游涵泳回遊録』を作り終えた時に、バンドとしてもっとオリジナリティ的な部分を磨いていって、より刺激的な、これを超える作品を作ろうっていう気持ちが凄く強くなったんですよね。 もちろん前作を超える作品を作ろうっていうのは毎回思うことなんですけど、特にそういう意識が強かったのが今回やったんです。けど、そうやって自分達のオリジナリティとか個性みたいな追求すればするほど、難しいなと思う面もあって……そこにおいて、自分との闘いがたくさんあった制作だったなと思いますね。だから正直、悩んだ部分は凄くありました。でも結果的に、ちゃんと自分が好きだと思えるものを詰めて街にすることができたと思うし、そうやって詰めたものがフレデリックの新しい個性になってるなと思えてる。なので、『優游涵泳回遊録』とはまた違う角度からひとつ強い作品ができた感じはあるし、自分でも本当にいい作品だなって納得ができるものになったと思ってます」
――何においてもオリジナリティを打ち立てるというのはもの凄く大変なことであり、生半可なことでは達成し得ないことであるっていうのは前提の上で、今作を作っていく過程で康司くんが難しさを感じたのは具体的にどういう部分だったんですか。
康司「やっぱり、求められていることと自分のやりたいことの差、そのバランスの部分で難しさを感じることが多かったというか。……フレデリックというバンドはフェスの恩恵を受けながら進んできたバンドであるっていうのを自分は凄く感じていて。実際、これまで楽曲を作る上でも、メンバーと『フェスでどう鳴らせるか、どんな景色を作れるか』を話し合った時期もありましたし、フェスとの向き合い方がフレデリックのひとつのテーマになる瞬間もあったんですよね。もちろんその中でも常に自分が本当に好きだと思えるものをちゃんと作ること、自分が思う踊れる音楽、面白い音楽、長く聴いてもらえる音楽を成立させていくことを凄く大事にしてきたわけですけど、僕らも30歳を超えてバンドをやっていく中で、より、自分の好きに対して自由であるということが音楽のあるべき姿なんじゃないかっていう感覚が強くなってきて。 やっぱり自分自身が好きだ、面白いと思えることをやり続けないと自分が音楽を作る意味を見失いそうになる、路頭に迷っちゃう感があって………けど同時に、自分達の音楽を肯定してくれる人達から貰っている恩恵も感じるし、そこに対して感謝もリスペクトも感じていて。それこそ自分達がオリジナリティっていう言葉を言えるのも、僕らが作ってきたフレデリックらしさを支持してくれた人達がいるからこそのことやと思ってるし。その中で改めて、そのバランスをどう取りながら自分の好きなこと、面白いと思うことを盛り込んでいくのか、そういう自分との闘いみたいなのが今回はより強くあって。特に『優游涵泳回遊録』を作り終えた後、今作に向けての最初の制作が“PEEK A BOO”と“ペパーミントガム”やったんですけど、あの時期は自分の中で闘ってる感じが凄くありました。で、そこから今回の作品を作っていく中で、『こういう答えが今の自分達の等身大なんじゃないかな』みたいなものを探っていった感覚もありましたね」
――今の話って、もちろんフレデリックが広がる契機となったフェスやこれまでフレデリックを支持してくれた人達に対する感謝とリスペクトという面があるのは理解しつつも、本質的には、「初期からこれまでの間に培ってきたフレデリックのアイデンティティ」というものを、「今の自分達が目指していきたいこれからのフレデリックのオリジナリティ」を踏まえてどう更新していきたいか、という話だと思うんですよね。当然ながら、人は経験と成長を重ねる中で音楽的な興味もどんどん変わっていくし、挑戦したいポイントも変わっていく。いつまでも20代前半の頃と同じであるわけがないし。
康司「そう、そうなんですよね」
――そういう意味で今作は、これまで自分達が作り上げてきたフレデリックのアイデンティティというものはありつつも、それを今の自分自身が抱く音楽的興味や挑戦をもって大きく刷新したい、そうすることで本当の意味で今のフレデリックの等身大の音楽、表現を作るんだ、ということに挑んでいった作品だと言えるのかなと、話を聞きながら思ったんですが。
康司「そうですね。だから自分自身にも凄く向き合ったし、同時に、今作を作っていく中で改めて、自分がやりたい音楽っていうのは自分達だけでは成立しない、相手の存在も凄く大きいんだなというのも実感しましたね。たとえば自分達のエゴだけで音楽をやったとして、それはそれで作品として満足いくものが出来上がるかもしれないけど、でも本来の自分達が好きな在り方というのは、自分達だけじゃない、相手も一緒になってフレデリックという音楽を楽しめる空間があること、そしてそういう空間を作っていくことだよなって思った。だからこそこれまでも、お客さんともちゃんと顔を合わせながら音楽を作り続けてきたんだと思いますし………そういう気持ちが歌詞にも出てると思います。だから本当に悩みはしたんですけど、結果的に悩むことが自分の原動力になっていった、アイディアを湧き立たせてくれるものになっていった感じもありましたね」
――3人にとってこの期間がどんなものだったのかはここまでのお話から感じることができたんですが、健司くんにとっては、前作以降の1年9カ月はどんな期間だったと思いますか。
健司「バンドというよりも個人的な話になっちゃいますけど、やっぱりこの期間は喉のことに向き合ってるほうが多くて。いろんな場所で話してる通り、ポリープに関しては(2023年の8月末から10月上旬にかけて休養を取り、声帯ポリープの切除手術を行った)めっちゃ落ち込んだり、もう歌えなくなるんじゃないかという不安を抱えて生きていたというよりは、もう5年くらいポリープを持ってることは知ってたので、その中であの時期に切る決断をしたという感じだったんですけど。ただ、不安はなかったですけど、やっぱり自分の歌に向き合うことは多くなったと思います。なんか、これは喉とは関係ないんですけど、この1年くらい体調を崩しやすくなって。というのは、前がちょっと過敏過ぎたというか、自衛し過ぎてたんですよね。 たとえばツアー中はまったくお酒飲まないとかだけじゃなく、日々の中で健康に気を遣い過ぎてて、これは何かあった時に爆発するんじゃないかっていう怖さを感じてた時期があったんですよ。でもよくよく周りのヴォーカリストの人を見てみると、当たり前にお酒を飲んで次の日にライヴする人も多いじゃないですか」
――はい、全然いらっしゃいます。
健司「それもめっちゃ破天荒そうな人というわけじゃなく、繊細そうなヴォーカリストの方でも意外とそういう人もいて。ということは、自分も過剰に健康に気を遣い過ぎながら生きるのではなく、もっと普通に生活する中で自分のコンディションを合わせていくほうがいいんじゃないかと思うようになったんですよね。で、そういう方向性で自分の生活を改善していった時に、逆に体調を崩した時の喉の使い方がわかってきたところもあって。『体調が悪い時はこういう体勢だと歌いやすいぞ』とか、マイナスの状況でプラスを見つけられることも増えてきて、それが自分の歌に対する新しい発見に繋がっていったところがあったんです。だから自分の喉に関する知識を増やすじゃないけど、そういう意識で自分の喉や歌というものに向き合うようになったんですよね。その結果、単純にポリープを切除したことによって明らかにできることが増えたというのも含め、総じて今まで以上に歌を好きになったし、歌というものへの興味も強くなった1年9カ月やったなと思います」
――今の話はつまり、以前は非常にストイックに健康管理をしていた――健司くんは基本的に真面目な性格だと思うので、それこそ常に万全の体調でライヴに臨まなければいけない、そのために徹底的に摂生しなければならない、みたいなマインドで日々を生きていたし、もちろんそれはプロとして凄く立派なことかもしれないけど、でも、じゃあ一生そういう生活を続けられるのか、それこそストイックな生活が続けられなくなった時にすべてが破綻するのではないかという怖さが自分の中にあった、と。
健司「そう」
――だとすると、生涯このバンドをやっていくために、もっとナチュラルに生きながら歌というものとつき合っていく方法を見つけたほうがいいんじゃないか、そのために生活を変えていきながら自分の喉と歌により向き合ったし、実際にそれが見つけられてきた1年9カ月だった、という話なんですかね?
健司「本当にその通り、言ってもらったまんまですね(笑)」
赤頭「カウンセリングみたいになった(笑)」
高橋「特にこの1年、健司くんのMCに滲み出る人間味がより濃くなったなと思うんだけど、そういう意識の変化も関係してるのかもね。体調管理とかをシビアにすればするほど、マインドへの影響が出やすくなるじゃん。ほんのちょっとのことが気になったり。そういうのを気にし過ぎないがゆえの心の軽さみたいなものが、MCの言葉にも出てるのかなと思った」
健司「確かに。なんか、いろいろラクになった感じはある」
赤頭「この前、ライヴ当日のリハで『健司くんの喉、今日ちょっと怪しいな』ってなった時があって。その後、僕ら3人で順番に健司くんの首をマッサージしたんですよ」
康司「全員でやったよな(笑)」
健司「その日、喉の周りの筋肉がめっちゃ硬くなってて歌いづらくて」
赤頭「で、健司くんは自分でずっと首を揉んでたんですけど、『それ自分だと揉みにくくない?』って言って、みんなでひとり10分ずつ揉むという」
健司「そうしたら本番はバッチリ歌えたから、功績は凄いありましたね。中でも武ちゃんが一番上手かった(笑)」
高橋「どこの筋肉がどこに効くか、理解してるからね(笑)」
――(笑)。年齢の話もあったけど、話を聞いていると総じて、まだまだこの先も長くフレデリックをやっていくために、高みを目指していくために、改めて自分達自身と向かい合って新しい挑戦をしていったミニアルバムなんだなと思いました。そしてそれはこの作品の音楽性にも表れていると感じます。
康司「うん、俺もそう思います」
01. CYAN
――ではここからは1曲ずつ話を伺っていきたいなと思います。まず1曲目の“CYAN”です。これはオリジナル劇場アニメ『数分間のエールを』の主題歌として書き下ろした楽曲で、非常にキャッチーな楽曲に仕上がっているんですけど、たとえば後半の間奏部分で、変拍子ではないんだけどシンコペを駆使して不思議な聴感をもたらすセクションが入ってきたりと、非常に新鮮な印象ももたらす楽曲でもあるなと思いました。
康司「“CYAN”は『数分間のエールを』というオリジナルアニメ映画の主題歌として書いたんですけど、映画自体がもの作りに対する葛藤みたいなところをテーマにしてるお話だったので、ちょうど当時の自分と重なる部分が凄く多くて。ものを作ることってやっぱりトライ&エラーの繰り返しだなと自分も実感してた最中でもあったので、あの間奏のところは、それを音楽的に表現したかったんですよ。リズムとしては4分の4拍子で綺麗に続いてくんですけど、でもその中でちょっとぶつかったり躓いたりしながら、それでも続いていくっていう、その様を表現したかった。結果、刺激的なアレンジになったと思うんですけど、そういう面白さをちゃんと意味のあるものとして入れたかったんですよね。……一風変わった刺激的なこととか奇抜なことって、意味がなくてもできることではあるじゃないですか。でも、僕は意味があることをやりたくて。ただ奇を衒いたいがために奇抜なことをやるのではなく、内に秘めてるメラメラ燃えるようなところを表現した結果、あるいは自分の好きを突き詰めた結果、変態性のある音楽になる、みたいな。で、そういう部分は経験を積んでスキルを磨いてきた中で、より武器になっていってるなというのは凄く感じてます」
――凄くわかります。この“CYAN”の間奏部にしても、アイディアがあってもバンドの演奏スキルがないと成立しないものですしね。
健司「あそこ、本当にムズいっすよ。普通に流れてるけど、みんなもの凄いことしてるで!?っていうのはいつも思ってます。対バンした人とも絶対にあの間奏の話になるんですよ。『あそこ、ワケわからんかったけどどうなってるん?』みたいな(笑)」
赤頭「ライヴでやり始めた頃はけっこうドキドキしたよな(笑)」
高橋「それは“CYAN”に限らず、いろんな曲に言えるよね。だからこそ、より気を引き締めてやるところもあるし」
康司「だからそれぞれのスキルが上がった結果、自分の好きなものを自由に出せている感じは間違いなくあって。たぶんそうじゃなかったら出てこないアイディアもありますしね。フレデリックのポテンシャルは、こういうところにもあると思います」
――健司くんはこの曲を受け取った時、どんなふうに感じました?
健司「今話した間奏パートも含め、全部に筋が通ってる曲になったなと思いました。自分達が今抱えているものだったり、今まで自分達が伝えたかったメッセージ、経験してきたものもちゃんと歌詞に入ってるから、タイアップ曲であると同時にフレデリックの曲として成立してる。そもそも映画のストーリー自体、自分達の感情とリンクする部分がたくさんあったからこそ、より繋がっている感じもあると思うんですけど。だからこそ、自分もこのメッセージをちゃんと歌に乗せようっていうのは意識しましたね。あと、この曲は特に、フレデリックのライヴでどういう景色になるのか、セットリストのどの位置に入るのか予想できなかった曲でもあります。あの間奏パートとか、フェスとかでやったら確実にお客さんを置いていってしまいそうじゃないですか」
――まあ、もしかしたらどうノっていいかわからなくて戸惑う人もいるかもしれないね(笑)。だけどそれがクセになる。
健司「そう、最初は『ようわからんパートあったよな?』って疑問に感じる人も多いと思うけど、それが入り口になって新しい面白さを感じてもらえるんじゃないかって。そうやってライヴでやっていく中でフレデリックの景色をどんどん更新していける曲やと思います。実際、今ライヴでやっている中でもそれは凄く感じてますね」
――武くんはどうですか?
高橋「さっき康司くんが言ってた、ちゃんと意味のあることをやりたいっていうのはドラムに関しても言えることだなと思ってて。今回のミニアルバムの中でも“CYAN”は特にそう思います。キックのパターンも、もの作りをしている人の心臓の感じをイメージして作ったんですよ。そこから発想して、だったら頭に実際に心臓の音を入れてもいいよなという考えで鼓動の音を入れたり。間奏もそうなんですけど、ちゃんと意志を持ってアレンジできた実感がある。それが凄く印象に残ってるし、得るものが多かった楽曲だなと思ってます」
02. 煌舟
――2曲目は“煌舟”です。4分で力強く跳ねるリズムの気持ちよさが発揮されていると共に、歌謡曲性の強いメロに宿る推進力や随所で出てくるクワイアが効いている曲ですよね。歌詞のメッセージもとても強いなと思ったんですけど、この曲はどういうふうに生まれたんですか。
康司「『CITRUS CURIO CITY』を作っていく中で、フレデリックの新しいリード曲になるような強い楽曲をどんどん作っていきたいっていう気持ちがあって。僕らが今目指しているのは、年に一度、アリーナツアーをできるバンドになるっていうことなんですけど、だからこそアリーナという大きな場所で音を鳴らす気持ちよさを体現した、アリーナを踊らせることができるダンスミュージックを作りたくて。で、自分達で舵を取ってそこに向かっていくんだというバンドの意志を歌詞に乗せて作ったのがこの曲ですね。船で大海を進んでいくといろんな揺れも感じるし、時には大波に襲われることもあるじゃないですか。それと同じように、自分って一体何なんだろう?とか、フレデリックって何なんだろう?って凄く悩んだ時もあるけど、でも実際に自分は自分にしかなれないし、そこに意味があると思うし……カッコ悪い部分もあるかもしれないけど、でも、それを恥じる必要はないなとも思うから。そういったことも全部持ち寄った上で、自分達のありのままに進んでいきたい。まあ、ありのままって言うと『ありのままとは?』という問いが出てきちゃうんですけど(笑)」
――(笑)。
康司「でも、自分達のあるがままに、好奇心を持って進んでいくことの面白さと重要性を、音楽的な表現や歌詞に乗せて打ち出す楽曲にしたくて、この“煌舟”を書きましたね」
――そのメッセージは今回のミニアルバムの随所で強く出てきますよね。この曲は<煌舟 舵取れ 己を勝ち取れ>という言葉から始まるんですが、それこそ“ペパーミントガム”にも<任すな 任すな 取り舵を>という言葉が出てくるし、“ハグレツバメ”にもそのマインドが表れていると思うし。
康司「そうですね。やっぱり自分達が30を越えてどうありたいかを考えた時に、より面白く音楽を鳴らす、より気持ちよく音楽を鳴らすために自分達が立ちたい場所へと向かっていきたいなと思ってて。だからこそ、自分達を応援してくれる人達に対しても新しいフレデリックの魅力や面白さをもっと伝えていきたいし、その人達が抱いてくれてる期待やイメージを超えていきたいわけで。その気持ちがどんどん強くなってることが作品にも出てますね(笑)。あとやっぱり、歌詞は健司のMCの言葉にも影響を受けてると思うし、バンド内で話してたことも反映されてると思います。実際に夢が叶うかどうかってことだけじゃなく、何か夢を持ってそこに向かっていく、その過程自体が素晴らしいと思ってるんで、僕らはその過程をちゃんと見せていきたくて。“ハグレツバメ”とか“ペパーミントガム”とか、他の曲でもバンドが前に向かっていく意志が表明されてるのは、その表れでもあるかなと思いますね。“煌舟”は特に、このアルバムのテーマ曲でもあるのかなっていうぐらい、その意志が強い曲だと思ってます」
――ですよね、パンチラインばっかりだもんね。
康司「パンチラインばっかりにしました(笑)」
――健司くんは“煌舟”、どうでした? メロディが新鮮であると同時に、これは健司くんの歌唱にとても合うメロだなとも感じたんですけど。
健司「そうなんですよ。最初にリード曲としてこの曲をレコーディングしたいって言ったのは自分なんですけど、メロが凄くいいなと思ったし、めちゃくちゃ自分に合ってるなとも思って。かつ、康司からデモを何曲かもらった中でこの曲が圧倒的に力があるというか――もちろんどの曲もそれぞれに力があって、共感したり心揺さぶられたりするものやったんですけど、“煌舟”は圧倒的に引っ張ってくれるのに寄り添ってくれてる、みたいな感覚があって。なので、歌に関しても自分がどう歌ったらいいのかっていうイメージもめちゃくちゃできたし。あと、これは『CITRUS CURIO CITY』全体に言えることなんですけど、この作品が完成した時に、ひと口に『自分とはどういうものなのか、自分はどうしたいのか』と言っても、それが『みんなから見てどういうものなのか』という視点ではなく、『自分の内側にいる本当の自分ってどうなんやろう』という視点に変わったような印象があったんですよね。で、やっぱりそれが一番頼れるというか。全体を見渡して自分のキャラを確立している人よりも、自分がやりたいことに真っ直ぐ突っ走って自分が構成されてる人のほうが、俺は面白いと思うんで。 だからこそ、より自分を深く探求していってる歌詞に共感するんだなと思ったし、それがこの8曲並んだ時に明らかに新しいフレデリックを構築することに繋がっているなと思って、凄く頼もしい気持ちにもなりました。さっき康司がアリーナっていう話をしてたじゃないですか。その話をひとつ補足しておくと、アリーナに立ったとしてもライヴハウスに立ったとしても、結局は自分自身が言葉を発して歌を歌って、それを受け取る『ひとり』がいるんだっていう意識が凄く強くなってるんですよね。アリーナの大観衆を前にしたとしても、そのひとりが1万人集まってるんだという、そういう感覚でフレデリックのライヴを成立させたい。自分は2年前くらいからそういう意識になって、そこからMCもちょっと変わったんですよ。『みんなに伝える』んじゃなく、『あなたに伝えるんだ』という意識で言葉を放つようになった。そういう想いは、康司の歌詞にも繋がってるように感じますね」
――この曲、間奏でちょっとエレクトロ的なアプローチが強まった上でギターソロが炸裂していくじゃないですか。あの感じはアリーナで映えそうだなと、とても思いました。
康司「隆児が凄くエキセントリックなギターソロを持ってきましたね(笑)。特に何も言わずとも自分がイメージしてたものを遥かに超えてきてた感じがあったので、それこそ頼もしく感じました。『優游涵泳回遊録』ぐらいからそういう瞬間がより多くなっていて、凄くよかったです」
――何を思ってあのソロになったんですか?
赤頭「うーん、でもあのソロは、康司くんのイメージを聞いて、けっこうそのままやったつもりなんですけど」
康司「全然そのままじゃなかったけどな(笑)」
赤頭「(笑)。俺としてはエキセントリックなイメージも特になくて。むしろちょっと古めのギタリストっぽいソロというか。ただ、フレデリックではあまりやってこなかったジャンルという意味でのユニークさみたいなことは考えたかな。そこは康司くんも受け入れてくれるやろうなっていうのはあったから、『これでどう?』って言いやすかったのはあります(笑)」
――イントロから繰り返し入ってくるクワイア部分の歌詞は、歌詞としては表記されてないんですが、あれはみんなで歌いたい箇所ですね。
健司「うん、あれは歌いたくなるよな」
康司「歌詞として表記しなかったのは、謎の呪文を言ってる感じのほうが気持ちいいなと思ったからで。自分は昔から『これ、なんて歌ってるんだろう?』みたいな部分にワクワクするタイプだったんで。でもきっと、みんな何となく歌ってくれるんじゃないかなって期待してます(笑)」
03. Happiness
――“Happiness”というタイトルだし、曲調的にも非常にユーモアと楽しさを感じさせる曲ではあるんですけど、この曲のベースにあるのは世の中に対する憤りであり、痛烈な皮肉がたくさん歌われた楽曲です。フレデリックは折に触れて世の風潮に対してアンチテーゼを表明する曲を作ってきていますけど、これもそういう楽曲のひとつなんじゃないかなと思いました。
康司「皮肉を歌う曲みたいなのは、“CYNICALTURE”だったり“正偽”だったり、昔からいくつかあって。そこはその都度その都度、自分が楽曲を書く上での原動力にもなってる部分ですね。この“Happiness”も自分が幸せに生きていくことに対して凄く考えた時期があって。自分が幸せだと思うものが消費されていくスピード感が凄く速いなと感じていて……あっという間に消費されて消えていくものの中にもたくさんの意味や重みが託されてるのに、その一部分だけを貪り尽くすみたいな、そういう風潮に疑問を感じることが多いというか、その波に同調することへの違和感が凄くあって。自分はやっぱり、自分が面白いと思ったものを深く探求したいんですよね。それこそ映画1本見るにしても、どんな監督がどんな想いを込めて作っているんだろうとか、このシーンにはこんな意味合いがあるんじゃないかとか、そういうのを調べるタイプなので。そういうことを思いつつ、その上で幸せということに対して自分がどういうメッセージを発していけるかを考えながら、皮肉も交えて面白おかしく書いた曲でもあります」
――武くんはこの曲をどういうふうに捉えました?
高橋「今回のミニアルバムが出来上がって過去の作品と比較した時に、芯を食った言葉選びがめちゃくちゃ多いなと思ったんですけど、“Happiness”に関しては特にそういう印象を持っていて。で、リリースの順番的にもその前に“CYAN”があって“Happiness”っていう流れで、康司くんの気持ちの内側の部分が凄く出てるなと思ったからこそ、そこに対して自分なりに正しく向き合いたいなと思った時に、僕自身の内側にある葛藤みたいなものを正直に音に出してレコーディングすることが正解な気がしたんですよね。なので、そういう気持ちでレコーディングしました」
――健司くんは?
健司「僕は痺れましたね。ヤバい曲を書いてきたなっていうのがまずあって。今までの康司のメッセージの中でここまで芯食ってガッツリ毒のある、でも最終的に確実に救いがある楽曲をシングルとして出してくることってあんまりなかったんですよ。でも、このタイミングだからこそこれをシングルとしてちゃんと出したいっていう想いもあったし、ライヴにおいてもこういう曲は今絶対に必要だろうなと思って。ただ単にノッて楽しむというよりは、『はぁ……すげえもん見せられた!』っていうような気持ちにさせる、そういう感覚でその場を埋め尽くすようなライヴになるだろうなって想像もできたし。なので、自分としてはそこをどう表現していけるんだろう、みたいなところは考えつつも、歌に関してはあんまり自分の感情を乗せ過ぎないようにしたというか。これは自分あるあるなんですけど、歌詞が鮮明に芯を食ったこと言ってる時ほど、あまり感情を乗せ過ぎないっていうのは意識してて」
――純粋にその言葉を伝える媒介になる。
健司「そう。意識としてはそういう感覚でやりましたね」
――凄くメッセージが強い楽曲なんですけど、音は音で非常に楽しくて。特にベースソロからギターとユニゾンしていくところ、あの展開も凄くいいなと思いました。
康司「あれは俺と隆児の合作ですね。あそこのベースラインは元々自分で考えてはいたんですけど、隆児が持ってきたものが凄いよくて、それによってこの曲のカオス感やスピード感がより出たなと思ったので採用しました。……あと、ひとつつけ足してもいいですか?」
――もちろん。
康司「“Happiness”を作るにあたって自分達にとっての幸せって何やろう?って凄く考えた中で、自分が『これめっちゃ楽しい、この瞬間よな!』みたいなことを思うのってやっぱりライヴだなと思ったんですよね。なので<優婉 優婉 You and me これだろ>っていう部分は、この曲の歌詞の中でも自分が一番大事にしてる場所で。そっち側に幸せがないんだったらもっとこっちに来いよ!みたいな気持ちがこのサビの部分に出てるというか。なので、自分達があなたと顔を合わせることができるライヴという幸せな場所の大切さも意識しながら書いた曲ではありますね」
04. sayonara bathroom
――この曲は非常に心に沁みる名曲だなぁと思いました。曲調的には淡々とした、非常にシンプルな構造のリフものなんですけど、本質的な部分で極めてエモーショナルな楽曲だな、と。
康司「ミニアルバムに向けていろんな曲を作っていく中で、展開が多い曲ばかりになってきていたところもあって、ここちょっと締めたいなっていう気持ちになって。元々自分でアレンジを作ってた時はもうちょっとコード感や動きがあった楽曲だったんですけど、でもドッシリした感じにもしたかったから、だったら恐れずにリフ1個押しで恐れずにやろうぜ、みたいな会話をしながら作っていきましたね。サウンド感としても、リフ1個で押すのはなかなかの冒険ではあるんですけど、アルバム全体の中でちゃんといいバランスに着地することができたんじゃないかなと思います」
高橋「僕はこの曲、本当に大好きで!」
康司「(笑)」
赤頭「やー、これはいいよね。俺ら3人とも大好きって言ってたよな」
健司「“sayonara bathroom”は全員一致でアルバムに入れたいってなったもんな。感覚的なところでこれはバンッとハマッた感じがあった」
――武くん的な大好きポイントはどこなんですか。
高橋「全体に大好きなんですけど、やっぱりBメロの歌詞がめちゃくちゃ刺さる。しかも康司くんがこの言葉を吐露してるということが、感動を倍増させます。……なんか、最近言葉にするの苦手になってきて(笑)」
――ははははは。
高橋「言葉にすると、どうしても感情がその言葉に寄っていく部分があるじゃないですか。でも今は、感動をそのまま捉えて音にすることに凄く美しさを感じるようになっていて。ちょっと前の自分は筋が通ってる話のほうが好きだった傾向があるんですけど、最近はもっと感覚的なものを大事にしたいなと思うんですよね。なのでこの曲に関しても、デモを聴いた時点での感動をそのまま音にしたいっていう気持ちが強かったがゆえに、『大好きです』以外、今は言えないっていうのがあります(笑)」
――わかりました(笑)。でも私も、<正しさなんてさ/誰が決めたんだろうな>という箇所を筆頭に、この歌詞は本当にグッと来るなと思いました。なのでぜひリスナーの方にも噛み締めて欲しいんですが、隆児くん、リフも含め、ギターに関してはどうですか。
赤頭「リフに関しては康司くんが作ったデモが凄くいいなと思ったから、それをカッコよく弾くことに全力を尽くしました。“オドループ”とかもそうなんですけど、康司くんが作ったものをカッコよく弾いて、その上でソロをもらったからには、ソロをよりカッコよくしたいなっていう意識やったかな。今までは割とギミックっぽいソロとか、スタッカートでちょっとシュールなソロみたいなのを多くやってきたんですけど、さっきの年齢重ねる系の話じゃないけど、こういうニュアンス重視のソロみたいなものもやってみたいなと思って。楽しかったです」
康司「隆児がこのギターソロを持ってきた時、凄くいいなと思って。年齢を重ねてより渋みが出るみたいなところってギタリストには重要なところだと思うし、あとこのソロに関しては、特に自分がやりたいことというか、自分のギターはこうあるべきって話を隆児が凄く丁寧に話してくれたんですね。これを広がりがある会場で弾いた時に自分がどう鳴らせるか、それによってどう感動できるかっていう、そういう話を等身大で語ってくれたのが印象的やったし、レコーディングの時に改めて弾いてくれたのを聴いて凄くしっくり来て、これが正解やなって思えた。そういう隆児の想いがギターを通して強く反映されたのは、作品としても一段階上げてくれたんじゃないかなと思う、それくらい素晴らしいギターソロやと思います。今フレデリックの楽曲の中でナンバーワンですね」
赤頭「やったー!」
05. ひとときのラズベリー
――この曲は割とスッと聴ける曲ではあるんですけど、2Aでビートチェンジしたり、細かく転調もしていたり、実は随所で音楽的な表情が変わっていくし、様々な趣向が凝らされている楽曲ですよね。
高橋「確かに。各パートの跳ね具合とか、シーケンスの感じとかもみんな違くて。でもスッと成立しているというのが、フレデリックじゃないとできないノリになってるなとは思います」
康司「これは自分の書きたいJ-POP像の新しい完成形を目指せた曲で。サビもフレデリックっぽいリズムではあるけど、コードの感じが急にグッと変わる表現にゾクッとする感覚があって――」
――<あなたとわたしの夢の中>のところですよね。あそこ、とてもいい。
康司「そう、これを上手く表現したかったんです。ここのひと捻りは凄くこだわりました。自分の好きな歌謡曲感だったりメロディ感だったり、それに加えて健司の歌をどういう活かすのかを追究した中で、このメロディの作り方っていうのは自分の中でひとつ発明感があって。作ってる時、凄く楽しかったです」
高橋「曲の短さもいいよね」
康司「そうそう、このサッパリ感というか」
高橋「サッパリ終わるがゆえに余韻が残る感じがして」
健司「俺もまさにそう思う」
康司「甘さと酸っぱさが共存してるっていう、凄く不思議な感覚があって。『CITRUS CURIO CITY』っていうタイトルを決めた時も、柑橘系の酸っぱさというか、苦味や酸味を感じるのに爽やかな気持ちになれるという、むしろ苦味があるからこそそこに辿り着けるっていう感覚が、まさに自分が曲を作っている過程だったり、今感じていることに凄く合ってる感じもして。そういうところも含めていいなと思ってる楽曲です」
――これは歌っていて気持ちがいいんじゃないかと思うんだけど、難しい?
健司「難しいと思ってたんですけど、めっちゃ気持ちいいです。さっき言ってた箇所もそうやし、とにかくこの曲は全部のメロディが主役になってる感じがめっちゃ好きで。サビのためのAメロとかでもなく、AメロはAメロでちゃんといいメロディがあって、BメロもBメロでちゃんといいメロディがある。全部キャッチーやし、聴いていて心地よさもあるから、そういうところにめっちゃ魅力を感じてますね。2A後半でメロが変わるのもめっちゃいいし」
赤頭「この曲、実はリード曲にしようかっていう話もあったんですけど、アルバム曲になったことでアレンジの方向性がちょっと変わったというか、僕の中では自由度が増した感覚があって」
康司「パンチ力があるかどうかとかではなく、より楽曲としての面白さを追求したがゆえのアレンジになったということ?」
赤頭「そうそう。だからコード進行はしっかりあるんですけど、ギターではそのコード進行を追いかけず、トップの音を統一してちょっとクールな感じ、かつファンキーな感じにしたくて。上手くできたなと思います」
06. ハグレツバメ
――そして“ハグレツバメ”です。非常に気持ちのいい、しなやかに雄大な景色を切り開いていくような楽曲なんですが、この曲も今のフレデリックの演奏力の高さ、4人が放つグルーヴの抜群の気持ちよさが効いてる曲だなと思いました。全員の呼吸がしっかりと合ってないとこの心地よさは出てこないなと思いますし。で、歌詞もとても強い、ひとつの決意表明として響いてくるリリックになっているなと感じました。
康司「そうですね。曲が進行するにつれて展開が変わっていく中でもずっと気持ちよく聴かせられる感じができたのはよかったです。歌詞に関しては、フレデリックをよりビルドアップさせていく上でより自分に向き合わなきゃいけないっていうところを歌詞にしたくて。……音楽や芸術って突き詰めれば突き詰めるほど孤独感が増していく感じもあるんですけど」
――はい。
康司「今回のアルバムは特にその孤独感と向き合っていった感覚があるんですけど、そうやって自分と闘い続けた時に、万人に共通する孤独感に近づく感じがしたんですよね。で、きっとそれが自分の描きたい音楽なんだろうなと思って……この曲はそれが表現できてる楽曲だなと思うし、これからのフレデリックへのメッセージにもなっていく楽曲だと思いますね」
――孤独感はありながらも、サビ終わりの<ずっと ずっと 遠くへ 遠くへ>でスッと音数が抜かれるじゃないですか。あそこで重力から解き放たれるような感覚もあって、それが凄くいいなと思ったんですけど。
康司「あそこはまさに、飛べる感じをイメージしていて。この曲のイメージとして、孤独って重いものでもあると思うからこそ、軽やかさみたいな部分も表したいというのが自分の中にあったんですよね。ひとりでいる時に感じる孤独だけじゃなく、みんなでいる時に感じる孤独もあるじゃないですか。この曲はどちらかと言うとそれをイメージしていて。そう考えた時に、そこから解き放たれて軽やかに飛んでいく感じを表したかったというか。……ツバメって自分の行き先を覚えてるというか、自由に空を飛びながらもちゃんと故郷に帰っていくじゃないですか。バンドもしっかりと自分達が目指すところに向かいながらも、その自由さと軽やかさみたいな部分は持ち続けなきゃいけないなと思うんですよね。 やっぱりやればやるほどどんどん重しを課せられるというか、背負わなきゃいけないものも増えてくるけど、でも軽やかにどこへでも飛んでいって、いろんな音楽性を面白がりながら、自分達が辿り着きたい場所へ辿り着いていく……そういうふうに進んでいくことがフレデリックの面白さだと思うし、そこに関してはもっと意識していかなきゃいけない部分だと思ってるんで。なので、そういう俺らの意志が聴いてくれる人にもメッセージとして強く届いて欲しいなっていう気持ちと、同じ想いを抱えている人達にとってエールになって欲しいなという、そういう気持ちで書きました。だから“ハグレツバメ”ではあるけれど、誰かの孤独に寄り添えるような楽曲になっていったらいいなと思って作ってましたね」
――その想いは言葉だけじゃなく、このメロディとサウンドアレンジからもしっかりと伝わってきます。
康司「ありがとうございます。サウンド感と言葉がちゃんとリンクしてる部分は、今回の作品でより強まっていってる感覚はありますね」
07. PEEK A BOO
――“PEEK A BOO”はとても面白いというか、軽快で小粋なダンスビートのセクションと、景色がぐんにゃりと歪むような幻惑的なサイケ・セクションが交錯する、いい意味でかなりヘンテコな曲ですよね。
健司「これを作ったの、もうめちゃくちゃ昔な感じするなー」
高橋「確かに昔な感じする(笑)」
健司「レコーディングは“ペパーミントガム”と一緒のタイミングかな。去年の8月とかにレコーディングしたような気がする。まだポリープがある時期、手術前に“ペパーミントガム”と“PEEK A BOO”は録ってるから」
康司「“PEEK A BOO”と“ペパーミントガム”が、『優游涵泳回遊録』の後、最初に作った曲やったもんな。『優游涵泳回遊録』をリリースしてから、次も何かもっと刺激的な、より面白いことがしたいよね、みたいな会話が最初にあって、その中で自分達の好奇心的な部分を大事にしながら作り始めた曲だったと思いますね。今までのフレデリックの中にあるヘンテコさをより面白い形にして、今までにないものを作り上げようっていうところを話し合った中で生まれたのが“PEEK A BOO”やったと思う」
――“PEEK A BOO”も“ペパーミントガム”もサイケみの強いセクションがあるのは、今話してくれた「今までのフレデリックの中にあるヘンテコさをより面白い形に」というのが関係してるんですか。 要は、初期のフレデリックの要素をもう一度見つめ直してみよう、みたいな。
康司「最初に話したオリジナリティみたいなところでの悩みに直面してた時期が、まさにこの2曲のタイミングだったんです。その中で本来の自分達らしさって何なんだろう?みたいなところと向き合った時に、やっぱりこういうサイケな部分って自分の中に根強く残り続けてるんですよ。リスナーとしてもいまだにそういう音楽は好きで、自分がおぉっ!となるような音楽ってどこかにサイケな部分があったりする。それってもう自分の身に染みついてるものだし、素直に好きだって言える部分だからこそ、そういう自分の欲も凄く詰まった2曲になったなと思いますね。で、そうしたら隆児も“PEEK A BOO”のラストのところでめっちゃえげつないシンセを入れてきたんですよ」
赤頭「えげつない(笑)」
康司「それがよかった(笑)。この曲を作ってる時に隆児が『こういうところに康司くんらしさをめっちゃ感じる』って言ってくれて、それも嬉しかったし。自分の根本にある部分だから。なので、その面白さにフィルターをかけることなく、改めて素直にやってみようっていう気持ちで作っていったところもありますね」
――健司くんは“PEEK A BOO”を受け取ってどんなふうに感じましたか。
健司「オリジナリティについて悩んでた時期に大正解を叩き出した感じはしましたね。アルバムを通して聴いてもいい意味で異質感があって、『このアルバム、ヤバいやん!』ってなるポイントのひとつになってるというか。で、それはたぶんこのミニアルバムに限らず、最終的にこのバンドのキャリアを俯瞰した時にも『“PEEK A BOO”ヤバいよね』ってなる曲だなというのは、曲ができた時点で確信しましたし、ここからまたフレデリックは面白くなっていくんだろうなという期待を確実に強めてくれた曲やったなと思います。『優游涵泳回遊録』ができた後、次に向かう第一歩としてめちゃくちゃ相応しい曲になったな、これは面白くなるなと思いました」
――これ、ギターのフレージングも面白いですよね。
赤頭「うん、面白いですよね。さっきえげつないって言ってもらった最後のシンセも康司くんと一緒に作っていったんですけど、この曲の自分の役割的には3人を煽って3人に煽られる、みたいなのがいいのかなと思って。だから最初は、ラストも繰り返しにしようかなっていうアイディアもあったんですけど、この曲は行くとこまで行き切ってみるのもありやんな、1回やってみようって言って、全部メロディを変えてやり切ってみました。そこに関して康司くんとやり取りしていく時も、『じゃあこういう感じはどう?』みたいに楽しくできて。自分では凄く満足してるので、みんなにも楽しんでもらえたらよりいいなと思います」
08. ペパーミントガム
――キラキラと瞬くような音から始まりつつ、前半は割とベースラインが主役になっているところから表情豊かに展開していく曲なんですけど。ちょっとしたギターの音の質感やリズムのアプローチ含め、さり気なくも非常に練られた印象のあるサウンドと、憂いと哀愁を帯びた歌がとてもいい形で融合した楽曲だと感じました。
康司「『CITRUS CURIO CITY』の楽曲達って、そんなに意識してたわけではないんですけど、やっぱり歌謡曲の流れが好きなんだなっていうのを改めて感じる部分もあって。“ペパーミントガム”は特にそれを思いましたね。健司の声を通してフレデリックをやる上で、歌謡曲的なメロディがある楽曲って自分達なりのいい広がりが生まれるなと感じていて。“ペパーミントガム”や“ハグレツバメ”のデモを出した時も、健司が『お、この曲いいやん』って反応してくれたんですよ。“ペパーミントガム”はそうやって健司がいいと思ってくれる部分だったり、健司の声をより気持ちよく響かせていく中でフレデリックとして自分ができることをちゃんとできた曲なのかなと思います。ライヴでも凄く伸び伸びとやれてるし、このアルバムの中でもひと際輝く楽曲になったんじゃないかな、と」
健司「自分がデモを聴く時って、たとえばライヴでどういうふうにやれるかっていうプレイヤー目線で考えたり、自分がどう具現化したら面白くなるやろうなって考えたり、いろいろな目線があるんですけど、この“ペパーミントガム”や“sayonara bathroom”、あるいは“たりないeye”を聴いた時は単純に『この曲、好きやな』って思ったのを覚えてて。純粋に曲として自分が好きやと思えるからこそ残したいっていう、そういうふうに強く思えた曲のひとつですね。で、そういう曲って歌う時の押し引きやったり、ファルセットの使い方やったりも感覚的に掴みやすくて。とはいえ、好きから始まった歌はけっこう苦労しますね」
――そうなんだ?
健司「自分が好きと思ったところを再現したいがゆえに、こうじゃない、みたいなポイントも生まれやすいというか。自分の中でのハードルが上がるというか」
――なるほど。この曲の歌唱は凄くいいなと思いました。このバンドが持ってる歌謡曲性と健司くんの声が帯びている情緒が見事にマッチしているというか、そのハマりのよさみたいなものを改めて感じる曲でもある。
健司「こないだNew Acoustic Campに出た時に、アコースティックで“ペパーミントガム”をやったんですけど、むっちゃよかった」
康司「よかったなあ。なんか、歌謡曲性みたいなものって、時代の流れの中でどんどん変わっていってる感じもあるじゃないですか。そういったメロディじゃなくてもアリーナを埋めていくアーティストも多くなってきているし。けど、やっぱり自分達はこういう歌謡曲的な音楽って好きなんやなというのは、今回のミニアルバムを作って改めて気づいたところでもあります。どうしても自分達の中から出てきてしまう部分なんだろうなって思うし、ということは、それは自分達のひとつの強みやと思うから。なので、次の作品でも大事にしていきたい部分かもなって感じましたね」
――というわけで『CITRUS CURIO CITY』については全曲お聞きしましたが、最後に、2025年2月に開催される神戸ワールド記念ホール(2月11日)と日本武道館(2月24日)でのアリーナライヴ『FREDERHYTHM ARENA 2025』に向けての意気込みを聞かせてください。
康司「今回の作品を作っていく中で、フレデリックのアリーナをどういう場所にしていくかがよりはっきりと見えてきたところがあって。どのライヴも毎回、どういうテーマ性を持ってやっていけるかが重要だと思ってるんですけど、僕は『CITRUS CURIO CITY』という街は最終的には誰もがフランクに遊びに来ることができる街にしたいなと思ってて。たとえば、自分の故郷ではない場所に遊びにいった時に、そこがだんだんと自分の故郷、ホームみたいに感じられる場所になっていくのって凄くいいなと思うんですけど、今度のアリーナ公演が来てくれた人にとってのそういう場所になったらいいなと思っていて。この作品を通してアリーナに来てくれた人達と一緒にこの街を楽しめて、そこからさらに、また俺らと新しく面白いものを見に行こうって思えるようなアリーナ公演にしたいと思ってます」
高橋「このインタビューの中でも話した通り、今回の作品は芯を食った言葉選びが凄く多い、かつ、聴き手が自分の感情を乗せるだけの器の広さというのを凄く感じる楽曲達だなと思っていて。それって、演奏する側もそうなんですよ。自分の中にあるいろんな想いをこの音楽に乗せて表現できる曲達でもある。最初に健司くんが話してた『ライヴでどんな感じになるか想像がつかない』っていうのは、そういうところにも紐づいているんじゃないかなと思ってて。だからこそ今度のアリーナ公演を通して自分達でも想像してなかったような景色だったり、自分達が気づいてなかった各々の感情だったりを見つけることができるんじゃないかと思うし、それによってバンドを前進させてくれる作品になってるんじゃないかなと思うので。だから端的に、アリーナ公演が凄く楽しみです」
――ありがとう。隆児くんはどうですか。
赤頭「今まではアリーナ1会場だったのが、今回は2会場ということで、僕らにとっては挑戦でもあるんですけど、やっぱり凄く楽しみで。何やろうな………最近、僕もライヴでしゃべる機会が増えたんですけど、そうすると、より人と一緒にライヴを作っている感じがあるというか。もちろんその感覚は前からあったけど、より強まってるかな。健司くんが言ってた1対1で、みたいな話にも繋がるんですけど、目の前のひとりの人が楽しんでくれている実感みたいなものをより感じられるようになってるんですよね。だからその距離感でアリーナでもできたらいいなと思ってます」
――ちゃんと一人ひとりとコミュニケーションを取って、それを感じながらライヴをやりたい。
赤頭「そうです、そうできたらいいなって思います」
――ではラスト、健司くん、お願いします。
健司「最近、自分がライヴをやる時に思うのが、結局、何を持ち帰ってもらうのがいいんやろ、みたいなことで。自分が他のアーティストのライヴを観に行く時も、このアーティストは結果的に何をお客さんに届けて帰るんだろう、お客さんは何を受け取って帰るんやろうっていうのを意識して観ることが多くなってるんですよね。で、フレデリックのライヴを観て何を持ち帰ってもらえるんやろう、一人ひとりがフレデリックのライヴを通して何を見つけていくんだろうっていう、その答えはまだ探してる途中やり、きっと絶対的な答えがあるわけでもないんやろうなと思うんです。仮に自分の中で何か答えを持って臨んだとて、たぶんいざ武道館やワールド記念ホールに立った時にそれが変わるような気もするし。でも、確実に何かを持って帰れるような作品を作ってると思うから。今回の『CITRUS CURIO CITY』は特に自分達自身に向き合った作品だからこそ、聴いてくれる人自身も何かを見つけてもらえるんやないかって。……さっき話しながら何となく気づいたんですけど、自分がこの作品に対していい意味でライヴで想像ができないと思ったのは、たぶん受け取る人によって感じ方がそれぞれに違う曲達だからなんじゃないかなって。だからきっと、アリーナ公演から持ち帰ってくれるものもそれぞれに違うんだろうなと思うんですけど、それでいいんじゃないかと思えるようになってはいますね。それぞれ違う何かでいいから、確実に何かを持ち帰ってもらうライヴにしたい。そういう意味で1対1でちゃんと会話できるライヴにしたい、それによって何かを残したいという想いを持って挑みたいなと思ってます」
――自分にとっても思いがけない何かを見つけたり、交わし合えたりするライヴになるとといいですね。
健司「ね、何か見つかりそうな気がします。それが楽しみです」